行動経済学という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
IT系や学問好きのビジネスパーソンなら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
近年、ノーベル経済学賞を取り、GAFAMといった大手IT企業も注目する最新の経済学です。
この記事では、行動経済学について、そして伝統的な経済学との違い、学問としての意義を分かりやすく説明します。
行動経済学とは?

行動経済学は、経済学の一分野であり、人間の意思決定が必ずしも合理的ではないことを前提にしています。
伝統的な経済学である新古典派経済学は、人間が常に自分の利益を最大化するための合理的な選択をすると仮定しています。
一方の行動経済学は、人間が時に感情やバイアスに影響されて非合理的な選択をすることに注目しています。
例えば、スーパーで何かを購入するとき、あなたが特定の商品を選ぶ理由は、必ずしも価格や品質だけに基づくものではありません。
ブランドのイメージやパッケージのデザイン、さらには友人の意見など、多くの要因があなたの決定に影響を与えているのです。
行動経済学はこうした「非合理的」な人間の行動を理解し、予測しようとする学問です。
これまでの新古典派経済学
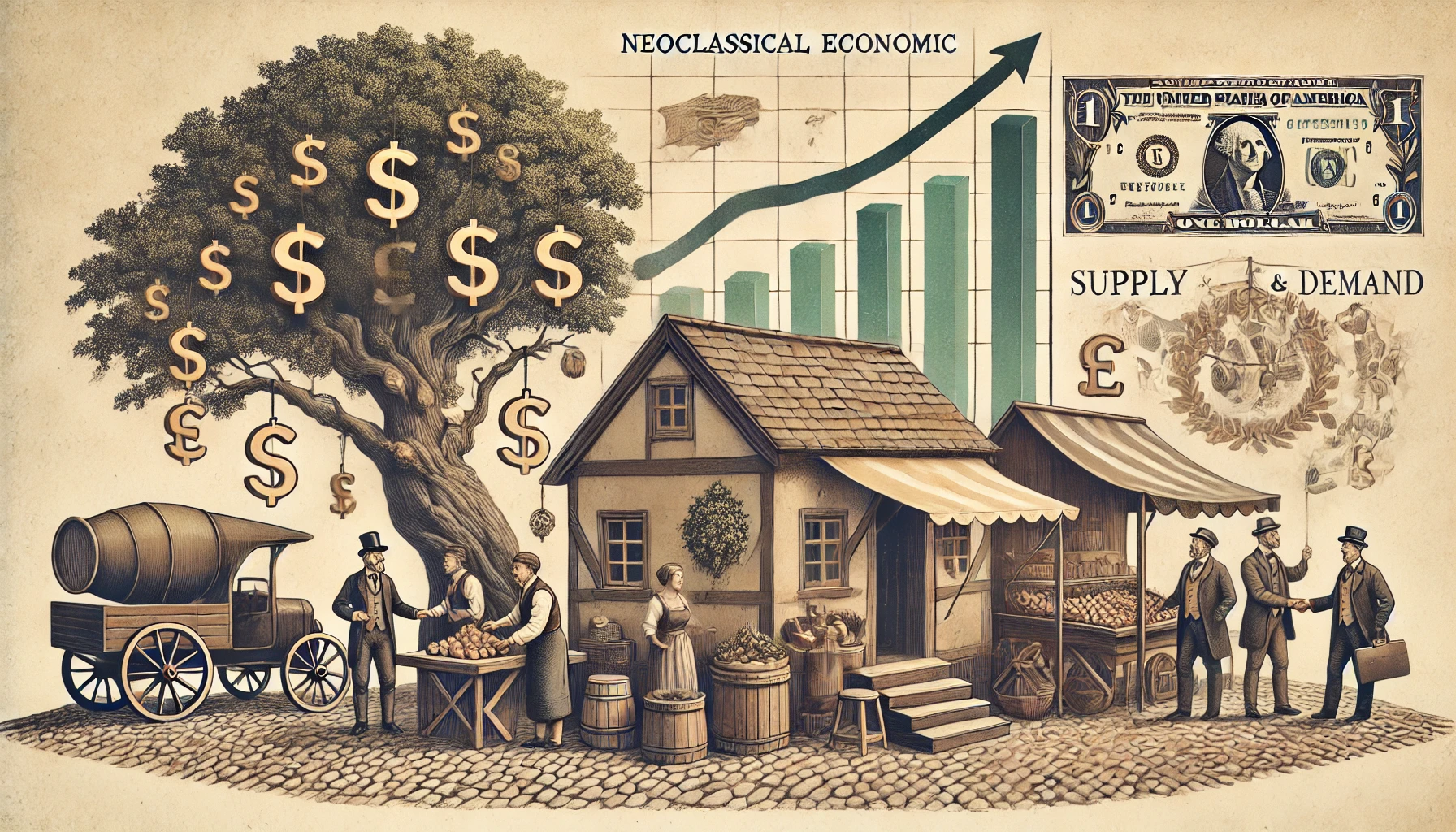
行動経済学について深く知る上で、まずは伝統的な経済学について理解しておきましょう。
行動経済学と、これまでの新古典派経済学はどう異なるのでしょうか。
ホモ・エコノミクスの仮定
新古典派経済学では、人間は「ホモ・エコノミクス(Homo Economicus)」と呼ばれる超合理的な存在であると仮定しています。
ホモ・エコノミクスとは、次のような特徴を持つとされています:
- 完全な情報を持っている – 市場に関するすべての情報を知っている。
- 計算能力が無限である – すべての選択肢を計算し、その中で最も合理的な選択を行う。
- 効用を最大化する – 自分の利益を最大化するために最善の選択をする。
この仮定に基づき、経済モデルが構築され、市場や経済の動きを予測します。
新古典派経済学では、実際の消費者はこうした完全な存在ではないとはいえ、ホモ・エコノミクスから乖離が小さく、説明できる範囲内だとしていました。
超合理性の意思決定プロセス
ホモ・エコノミクスの場合は、完全な情報、計算処理能力を持って効用を最大化します。
超合理性における意思決定プロセスは以下の三つの段階に分けられます。
- 与えられた選択肢の集合を定義する
- ある選択肢を選んだ時の結果を想定する
- 最も効用が高くなるような選択肢を選ぶ
また、新古典派の経済学者は、資本主義社会において自然淘汰が市場にも起こると考えていました。
すなわち、上記のプロセスに従わず、利益を最大化できない企業や、効用を最大化できない消費者は長期的には市場から排除されるため、ホモ・エコノミクス的振る舞いをするものだけが残ると考えたのです。
行動経済学の2つの大原則
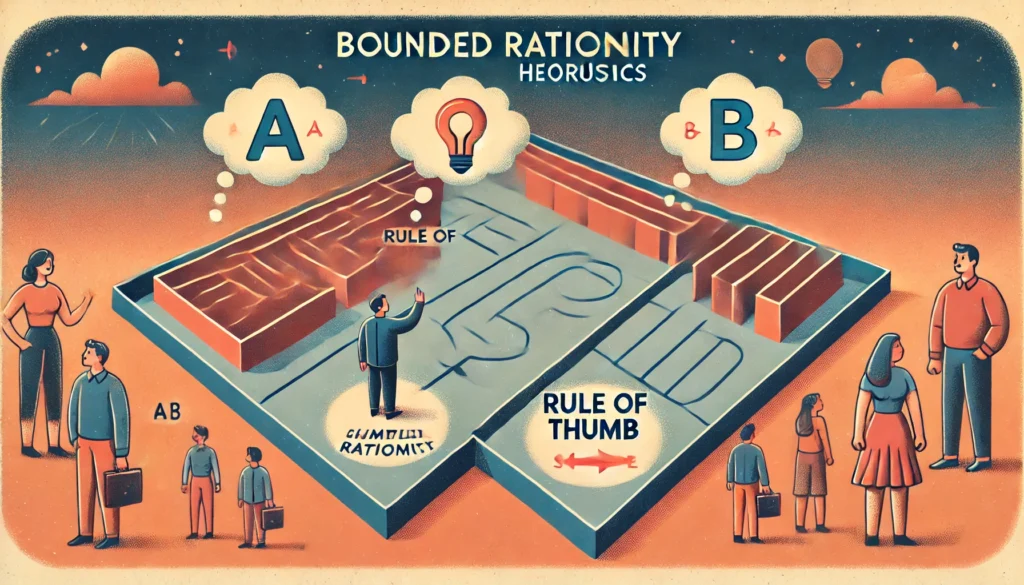
新古典派経済学の超合理性に対して、経済学者ハーバート・サイモンは人間の合理性をより適切に説明する限定合理性を提唱しました。
限定合理性とは、人間には認知能力や計算能力に限界があるため、完全に合理的な決定を下すことはできないという考え方です。
限定合理性
サイモンの限定合理性の理論は、以下の4つの段階に分けられます:
- 選択肢は内生的に発見される – 時間とコストをかけて選択肢を見つける。
- 結果の確率は主観的に評価される – 外部から与えられるものではなく、自分の主観で判断する。
- 効用は過程からも影響される – 選択の結果だけでなく、そのプロセスも効用に影響を与える。
- 選択肢の決定は満足化によって決められる – 効用最大化ではなく、満足できる選択をする。
これは、新古典派経済学の理論と大きく異なります。
限定合理性の理論では、実際の人間が情報の不足や計算の難しさ、感情的なバイアスなどにより、常に効用を最大化できないことを踏まえた、意思決定プロセスを表現しています。
ヒューリスティクス
ヒューリスティクスとは、人間が限られた時間と情報の中で意思決定を行う際に用いる思考のショートカットです。
進化の過程で迅速に「最適らしい」解を見つけることが可能であることは、アドバンテージをもたらしたのだと考えられます。
代表的なヒューリスティクスには以下の3つがあります。
- 代表性ヒューリスティクス: 人は典型的な例に基づいて判断を下しがちであり、ステレオタイプに影響されやすい。
- 想起しやすさヒューリスティクス: 記憶に鮮明に残る事例や直感的に浮かぶ情報に頼って判断する傾向がある。
- 係留ヒューリスティクス: 最初に提示された情報や数値に引きずられ、その後の判断を修正しにくくなる。
これらのヒューリスティクスは、効率的な問題解決を促進する一方で、バイアスがかかるため非合理的な決定を招くこともあるため、理解と注意が必要です。
行動経済学の歴史
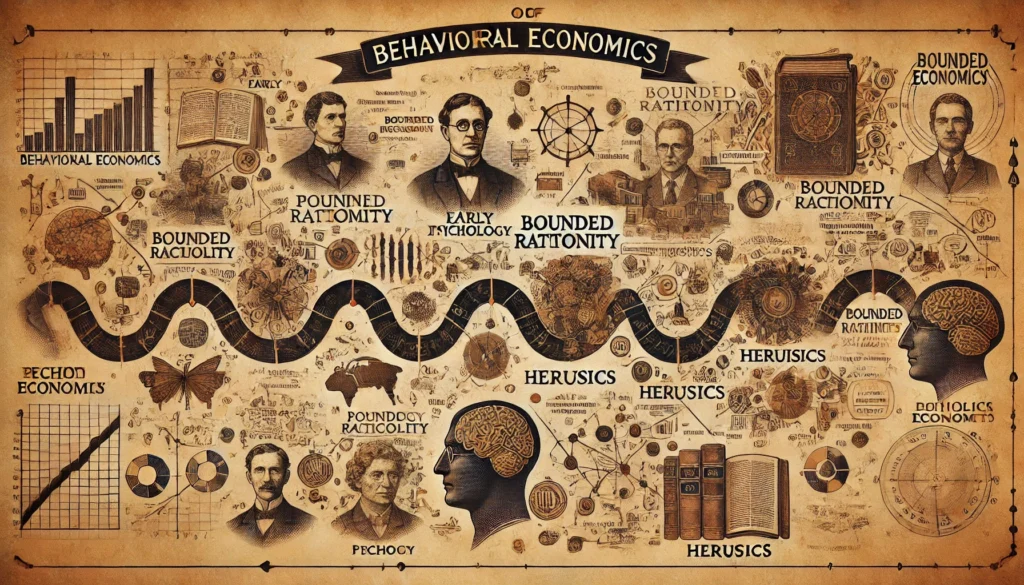
行動経済学は比較的新しい学問分野ですが、そのルーツは20世紀の中頃にまでさかのぼります。
初期の行動経済学: サイモンと限定合理性
行動経済学の基礎となる考え方は、1950年代にハーバート・サイモンによって提唱されました。
彼の限定合理性の概念は、人間が必ずしも完全に合理的な意思決定をするわけではなく、認知能力や情報処理能力に限界があることを強調しました。
サイモンは、この理論によって1978年にノーベル経済学賞を受賞し、行動経済学の礎を築きました。
20世紀後半の行動経済学: プロスペクト理論
行動経済学が本格的に発展したのは1970年代のことです。
ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーは、人間の意思決定におけるバイアスとヒューリスティックス(直感的判断)の研究を進めました。
彼らは、人々が意思決定をする際に合理的ではないパターンを示すことを証明し、その研究はプロスペクト理論として知られています。
プロスペクト理論は、人々が利益を得ることよりも損失を避けることを優先する傾向があることを示しています。
この研究により、カーネマンは2002年にノーベル経済学賞を受賞し、行動経済学はさらに広く認知されるようになりました。
21世紀の行動経済学: ナッジ理論
1990年代以降、行動経済学は多くの研究者によってさらに発展し、学問分野として確立されました。
リチャード・セイラーは「ナッジ理論」を提唱し、政策やビジネスの分野で実際に行動経済学がどのように応用できるかを示しました。
この理論に基づいて、政府や企業が人々の選択を望ましい方向に導くための介入方法が設計されました。
2017年には、リチャード・セイラーがノーベル経済学賞を受賞し、行動経済学の重要性がさらに認識されることとなりました。
今日、行動経済学はビジネスや公共政策の分野で広く応用されています。
マーケティング、消費者行動、ヘルスケア、エネルギー消費など、多くの領域で行動経済学の知見が役立っています。
行動経済学が注目される理由

なぜ行動経済学が注目されているのでしょうか。
行動経済学は、これまでの経済理論では見過ごされがちだった「人間らしさ」を取り入れているということでしょう。
現代の市場に適しているから
現代の企業は短期的な利益だけでなく、長期的な視点で利益を追求することが求められます。
特に現代においては、ESG経営が謳われるように、企業が利益だけでなく環境やダイバーシティなどの社会的意義も求められるようになっています。
超合理経済人であるホモ・エコノミクスでは、このような点は説明できません。
また、現代の市場経済において、消費者も非合理的な行動をしてもすぐに市場から淘汰されることはありません。
福祉国家においては、経済的に失敗した人々を支援する仕組みが存在するため、市場淘汰が機能せず、ホモ・エコノミクスだけが市場に残るという仮定は成り立たないのです。
より実践的で効果的なアプローチを導くから
行動経済学の知見は、特にマーケティングや消費者行動の分析において非常に有用です。
例えば、価格設定やプロモーションの効果を高めるために、消費者の心理的バイアスを利用することができます。
また、ナッジ理論に基づいた施策を通じて、消費者にとって望ましい行動を促進することも可能です。
このように、行動経済学はビジネス戦略の策定において強力なツールとなっています。
まとめ
行動経済学は、従来の経済学が仮定する超合理的な「ホモ・エコノミクス」ではなく、現実の人間がどのように意思決定を行うのかを探求する学問です。
ビジネスの世界では、このような人間の非合理的な側面を理解し、それに基づいた戦略を立てることがますます重要になっています。
ぜひ日常に溢れる行動経済学を探してみてください。



コメント